当社の昨年のM&A実績を評価されたことで、某有名M&A仲介会社から招待を受け、私はシリコンバレー・サンフランシスコでの国際会議に先月出席してきました。
会議では中小企業のM&Aの現状や成功事例についての報告、シリコンバレーの最先端のAI事情についてのディスカッションなどが行われました。
当社では順調にM&A実績を重ねており、折に触れてお話しをさせていただいていますので、当社のお客様周辺では既に、抵抗なく当たり前の選択肢の一つとして捉えていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。
しかし、会議に出席して実感したのは、世間一般の認識は、まだまだ中小企業のM&Aは「当たり前の選択肢」と言えるにはほど遠いということでした。
この会議は某有名M&A仲介会社の会員である総勢400名の税理士・公認会計士が日本全国から集まって行われたものですが、懇親会などで話しを聞いてみると驚くことに出席者の多くは、M&A実績がなく、積極的に顧問先に提案もしていないのです。
顧問先がM&Aで買われてしまうと顧問先が減ってしまうかもしれないという、税理士・公認会計士側の勝手な都合も無関係ではないようです。
つまり、某有名M&A仲介会社の会員になっている税理士・公認会計士ですら、実際に中小企業のM&Aに積極的に関わり実績を積んでいるのは、ごく一部なのです。
繰り返しになりますが、当社のお客様周辺ではM&Aは当たり前の選択肢の一つとして、既に認識が広がっています。
みなさんは、どうでしょうか?
もちろん、ご自身の年齢や自社の状況から考えて、今は縁がない話しだという方もいらっしゃるでしょう。しかし、経営者として中小企業のM&Aがどういうものかについては知っておいて損はありません。
損はないどころか、事業承継や自社の未来を考えた時に、M&Aを選択肢の一つとして持っていないことは、自社の、そして経営者自身の行く末に重大な相違が出てくる可能性は否定できません。
もちろん、実際にM&Aを行うか否かは別です。何もM&Aが常にベターな選択肢になり得るとは限らないのですから、当たり前です。
ただ、中小企業でもM&Aというカードがあるということを認識しておくことが重要なのです。
中小企業のM&Aには、きっとみなさんが想像していらっしゃるよりも、多くの形が存在しています。大げさに感じるかもしれませんが、M&Aが会社を、そして経営者個人の人生を救うことが本当にあるのです。
「うちの会社なんか買ってくれる人、いないでしょ・・・。」
「それに会社を売るなんて、なんかね・・・」
とてもよく聞く声です。
しかし、こうした方は多くの場合、中小企業のM&Aを誤解しています。
M&Aというと新聞やニュースで見る大企業のそれを想像している方がほとんどです。
しかし、中小企業のM&Aは大企業のM&Aとは全くの別物です。
もちろんM&Aには成功も失敗もあるのは事実です。
しかし、経営者として中小企業のM&Aがどういったものなのか、知っておいて絶対に損はありません。
当社では、当社グループのお客様限定ではありますが、事業承継のアドバイスの一環としてM&Aの仲介サポートも行っております。もし、M&Aに少しでも関心がおありなら、まずは身近な専門家に気軽に話しを聞いてみることから始めましょう。
自社を、経営者としての人生を、導く第一歩になるかもしれません。
赤字を出せるか?
旅行会社「てるみくらぶ」の経営破綻が話題となっています。
報道によると数年前から粉飾の疑いがあり、さらには税務署提出用と対外的説明用で決算書を複数作成し、信用調査会社には損益を非公開にしていたとのこと…。とても分かりやすい経営破綻ケースです。
職業柄、調査報告書はよく目にしますが、同一企業の調査報告書を毎年確認していくと、急に情報が非公開になることがあります。
非公開にするにはそれなりの事情がある訳で、状況が悪いという場合はその前年以前から推測可能です。
当然ながら、プロが財務諸表を見れば粉飾をしているか否かは概ね判断可能ですから、てるみくらぶも粉飾を始めた時期から非公開にしたのだと思われます。
ここ数年で粉飾騒ぎを起こしていた東芝も、さらに米国子会社の破産申請で上場廃止寸前まで追い込まれています。
粉飾が悪いという認識は万人にありますが、企業の安定的継続性のため(あるいは自己保身のため)に必要と判断して行うのでしょう…。しかし、粉飾は麻薬です。一度味を占めると断ち切るのが難しくなります。
てるみくらぶも早い段階で粉飾の連鎖を断ち切れれば、再出発が可能だったかもしれません。過去の失敗の清算という意味で、赤字を即座に出し切ることはとても重要であると考えます。
逆に、毎年絶対に黒字という結果には違和感を感じます。長年経営をしている企業に波風が立たない訳が無く、波風が立っているのに黒字を確保したというのは、単にどこかで調整を行っているだけに過ぎない場合があります。黒字を出し続けることが目的となり、結局は粉飾につながります。
大企業もダラダラと業績不振状態を続けた末に、大胆なリストラで大きな赤字を出すことがありますが、その翌年には「V字回復!!」を”演出”します。
演出という表現をするのは、先にまとめて赤字を出してしまえば翌年以降はその負担から逃れられることが分かっているからです。大したことをしなくても、結果として黒字になります。こういう面からも、赤字を出すときは一気に出し切る方がよいのです。
公開企業でもある大企業は周囲からも「リストラをするように!」と圧力が掛かりますから、最終的には赤字を出さざるを得ません。リストラをしたら支援を受けられることが分かっています。
しかし、公開圧力がない中小企業は粉飾を行いやすいこともあり、一度粉飾に手を染めると経営破綻まで赤字を出せなくなります。
今まで赤字を出されたことがないお客様が、不安から「この赤字をどうしよう…」とご相談いただくこともありますが、基本的には「そのまま赤字を出してみませんか?」とお答えするようにしています。
もちろん、残り少ない期間で打つ手を打ち、赤字を回避する場合もありますが(粉飾以外で)、赤字を「出せる」のであれば出していただく方が好ましいと考えています。
ちなみに、赤字を受けれたお客様が、その翌年さらに業績が悪化した例は見かけません。赤字を出したという事実から出発されれば、打つ手が明確になるからです。
なお、大企業によくあるリストラを行った”だけ”のV字回復企業のその後の業績を追っていけば、なだらかに下降曲線を辿っていることが分かります。
先に赤字をまとめて出してしまえば過去の負の遺産は清算できますが、そもそもの経営方針が変わらなければ、新たな負の遺産を作り上げるだけです。その後、さらにリストラを行いV字回復…。「V」ではなく、波のように「W」を繰り返しているだけです。これではシャープや東芝のように解体され続け、最終的には何の会社だか分からなくなってしまいます。
そして、赤字を出せない企業の特徴の一つに「不採算事業を止められない」があります。
てるみくらぶも不採算の本業を維持しようとした結果、経営破綻しました。
不採算事業をどれだけ継続しても赤字なのだと真に認識できれば(赤字の決算書を持って説明に回ることができれば)、経営の方向性が変わるのは必須です。外部からのアドバイスに耳を傾けることもできるでしょう。
赤字と正面から向き合える企業が最終的には生きながらえていきます。
赤字を出すにも準備が必要なのは間違いありませんが、安易に粉飾を行うのはリスクが付きまとうということも頭の片隅に置いていただければと考えます。
新「一筆」
調査官が「必要がある」と判断した場合に作成される『質問応答記録書』。
その作成趣旨については「調査において聴取した事項のうち重要なものについて、事実関係の正確性を期すために、その要旨を調査担当者と納税義務者等の質問応答形式等で作成するものである。」とされています。
これは平成25年6月に税務署が内部通達により、名称を『質問応答記録書』と定め、統一的な運用を開始したもので、要するに、調査の際に直接的な証拠がない場合などに、納税者の回答そのものを証拠とするために作成する書類で、業界では古くから「一筆」と言われてきたものです。
実は先日、私どもが顧問をさせていただいているお客様が、「取引先への調査に協力する」という場面において、『質問応答記録書』に出くわすこととなりました。
この『質問応答記録書』の本質がどういうものか、きちんと理解せずに署名捺印に応ずれば、取り返しのつかないことになってしまいかねません。
是非、この機会にきちんと理解しておきましょう。
さて、今回のことの成り行きはこうです。
A社に税務調査が入りましたが、調査の過程で代表者Bの個人口座に、私どもの顧問先C社から50万円の入金がある事実を調査官が掴みました。
しかし、代表者Bはこの入金を会社でも個人でも申告しておらず、かつ調査に非協力的であったため、調査官がその送金内容の確認のためにC社に協力の依頼をしてきたのです。
調査官からC社に対して協力依頼の電話が入った後すぐに、経理のDさんから私に連絡がありましたが、調査官が電話で話していた内容を聞いた時点で、ほぼ全容の推測ができましたので、事実をありのままに伝えるという形で税務署に協力してあげてくださいと伝えました。
真相は、代表者BがC社の商品を購入し、代金をA社の口座から振り込んで経費に計上したうえで、後にキャンセルし、その代金を個人口座に戻させることで、架空経費を作り上げていたというものでした。
当然、私どもの顧問先C社は、代表者Bのそんな思惑は知る由もなく、キャンセルの返金に応じただけですので、Dさんはその事実をありのままに調査官に伝えました。
ここで『質問応答記録書』の登場です。
後日、調査官はC社の経理Dさんの回答内容を『質問応答記録書』という形で文章に起こしてきたうえで、署名捺印を求めてきたのです。
当然Dさんは正直に事実を答えただけで、やましいことはありませんでしたが、初めてのことですので、戸惑うのも当然です。署名捺印に応じてよいものかと、すぐに私に連絡をくれました。
Dさんの回答内容が問題ないことは解っていましたが、万が一『質問応答記録書』に事実と違うことが書かれていたりすれば署名捺印に応じては絶対にいけません。
私はその場で調査官に電話を代わってもらい、私が内容を確認しないとDさんは署名捺印に応じられない旨を調査官に伝え、結果として電話口で『質問応答記録書』を調査官に読み上げてもらうという形で私が内容を確認しました。
記載内容は事実であることを再度Dさんに私から確認したうえで、署名捺印に応じても差し支えない旨を伝え、Dさんは署名捺印に応じました。
今回のケースでは、取引先への税務調査に対する税務署への協力ということで、内容的にも署名捺印に応じて全く問題のないケースでしたが、いつもそうとは限りません。
なぜなら『質問応答記録書』の本質はズバリ「課税するための客観的な証拠資料がない場合に、これをもって証拠資料とする」ことにあるからです。このことを理解せずに安易に協力してしまうと、それが原因で、みなさんにとって思いがけない、不利益な結果を招くことになりかねません。
仮に自社の税務調査において調査官が『質問応答記録書』を作成した場合、その記載内容が事実であり、修正申告に応じるつもりであれば、調査がスムーズに進み事業への影響も少なくなりますので署名捺印に応じるべきでしょう。
しかし、税務署の主張に納得していなかったり、記載内容や表現に事実と異なる点があれば話しは別です。
『質問応答記録書』は完成後に後日、訂正・変更の申立てをしても、訂正、変更等はできず、訂正、変更等の主張については新しい『質問応答記録書』を作成することによって対応することとされています。
つまり、一度完成した『質問応答記録書』は内容に誤りがあったとしても、削除されることはないのです。
税務署の主張に対して、十分に納得ができていない時点で、安易に『質問応答記録書』の作成、署名捺印に応じるようなことがないように、くれぐれも注意しなければなりません。
この書類はあくまで納税者の理解と協力を得て調査官が作成するものであり、みなさんが協力するか否かは任意なのです。
自社株の分散贈与の弊害
自社株の分散は、本当に相続税対策となり得るのでしょうか?
前回、株式の分散を防ぐ「相続人等に対する株式の売り渡しの請求」についてお伝えしました。地味ですが、とてもとても重要なお話です。
しかし、これは既に株式が分散されてしまっている場合の、緊急避難的な防御策です。時限爆弾が炸裂しても被害を最小限に抑えるための手段に過ぎません。
株式が分散していないのであれば特に気にしていただく必要はありませんが、基本的には全ての中小企業が加えるべき定款の記載事項です。
さて問題は、この条項を導入してあるからといって、株式を分散したままでよいのかという点です。
株式を贈与により分散させ、相続税の減額に成功したとしても、後に後継者は有償で買い集めなければなりません…。最終的には後継者が困る結果となり、本末転倒です。
例えば、既に兄妹間で株式が分散保有されている状態で、かつ、後継者も決まっているのであれば、徐々に株式を後継者に集めるということが可能です。
分散保有されている株式というのは基本的には贈与されたものであるため、誰も損をしておりません。従って、現オーナーの指示で分散されたであろう株式は、同じく現オーナーの指示で後継者に集中させることができます。
ただ、後継者に株式を集中する前に、贈与を指示したオーナーが亡くなったとしたら…。
贈与により異動した株式が、再び贈与により無事に戻ってくるなど甘い考えは捨ててください。生前にオーナーが株式を孫に大量に贈与しており、後々、後継者が甥や姪から有償で買い取らざるを得ないなんてことも十分に考えられます。
後継者ではなく、会社自身が自己株式として株式を買い取ることも考えられますが、そのための資金手当てを準備している会社は少ないものです。
29年度の税制改正で自社株の評価方法に変更がありました。これがどう転ぶかはケースバイケースですが、自社株対策を行わなければならないような企業の株価は上がり続けているとお考えいただくのが間違いありません。
おそらく、この1年でもかなり上がっているはずです。当社のお客様で試算を行っていますが、小手先の対策ではどうにもならないような上がり方です。いずれ下がるかもしれませんが、株価がピークのときに事が起こったら目も当てられません。
また、M&Aを視野に入れている企業にとっては、現状の株主構成はとても重要です。中小企業が事情譲渡を行うということは、換金することができないと思っていた株式が突如換金できるようになるということです。
換金できないからこそ気にしてこなかった株主構成が、換金できるとなると途端に重要な意味を持ち始めます。本来、事業承継に無関係であるはずの従業員に持たせている会社も見受けられます。
タイミングによっては、これまでゆっくりと無税で贈与してきた株式を、贈与税を払ってでも数年で一気に集めなければならない場合もあるのです。
つまり、事業承継の選択肢によって、現在の株主構成をどのように変化させていくのかというのはとても重要なのです。
なお、自社株式は後継者のみに引き継がせていくという方針の企業は問題ありませんが、この場合は逆に相続税対策が急務になります。
どれを選択してもお金が掛かりますが、事前対策によってその金額は大きく変わりますので、自社株対策をよくご検討ください。
自社株の分散を定款で防ぐ
定款は、会社設立の際に必ず作成する書類で、言わば会社の憲法にあたるものです。
それにもかかわらず、多くの方が会社設立の際に司法書士にその作成を依頼し、その後は机の引き出しにしまいっぱなしで、自社の定款にどういったことが定められているかを知りません。
繰り返しになりますが、定款は自社の憲法にあたるものです。
ほんの一文が定款に記載されているだけで自社を救うことができることがあることも、あまり知られていません。
中小企業経営者の相続で必ず生じる自社株の承継問題。
その中でも相続を原因とした株式の分散という問題を、よく見聞きします。
株式は後継者が既に決まっていれば、中小企業では通常、その後継者に集めるようにします。しかし、これが必ずしも上手くいくケースばかりではありません。
後継者が決まっていない場合や株価が高すぎる場合などに、とりあえずの相続税対策として複数の子供たち(兄弟)に分散して株式を取得させているといったケースがよくあります。
また、他に目ぼしい相続財産がないために、事業を引き継ぐ意思のない兄弟の手に株式が渡ってしまっていることもあります。
そうこうしているうちに、後継者ではない株主であるその兄弟にもしものことが起こったら、どうなるでしょう。そうです、兄弟の配偶者の手に株式が渡ってしまうということが、起こり得ます。
兄弟の配偶者といえば完全に他人です。
会社としては必要以上の株式の分散は避けたいところですが、実際には様々な事情により株式が後継者以外の人間だけでなく、あろうことか他人に分散してしまうということも十分に起こり得るのです。
分散した株式は、その株主が亡くなれば相続によってさらに分散して承継され、どんなに会社にとって望ましくない人物であろうと、会社は相続人を新たな株主として扱わざるを得ません。
会社としては、望ましくない人物に株式が相続されることは、なんとしても避けたいところですが、個人株主の相続を防ぐことはできないのです。
しかし、このような最悪の事態を防ぐことのできる、実に簡単な方法があるのです。
それは、自社の定款に次の条項を定めておくことです。
(相続人等に対する株式の売り渡しの請求)
第〇条 当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
定款にこの定めがある場合には、相続があったことを知った日から1年以内に株主総会の特別決議を経て、会社は相続人に対して株式の売り渡しを請求することができます。
つまり、相続で望ましくない株主の手に株式が渡ってしまった際には、この条項を定めておくことで、会社の判断でこの相続人に対して株式の強制買取をすることができ、望まない株主への株式分散を防ぐことができるのです。
これは平成18年5月1日の会社法施行によって新たに作られた制度のため、それ以前に設立された会社については、定款変更をしていない限り定められていないはずです。
また、会社法施行以降に作られた法人であっても、定款作成を依頼した司法書士によっては、この条項を定めていないことも珍しくありません。
もし、自社の定款にこの条項が定められていない場合、できるだけ早急に定款変更をしてしまうことをお勧めします。
しかも、この定款変更については、設立時には必要であった公証人の認証を受ける必要もなく、変更の内容が登記事項でもないため登記申請も必要ありません。株主総会の決議を経て定款に先ほどの条項を書き加えるだけでいいのです。
当社に株式承継のご相談をいただくケースの多くは、定款にこの条項が記載されていないため、まずは定款変更をご提案させていただくことがよくあります。
繰り返しになりますが、公証人の認証も、登記も要りません。株主総会の決議を経て、ただ定款に条項を書き加えるだけでいいのです。
とりあえず今日、自社の定款を確認してみてはいかがでしょうか。
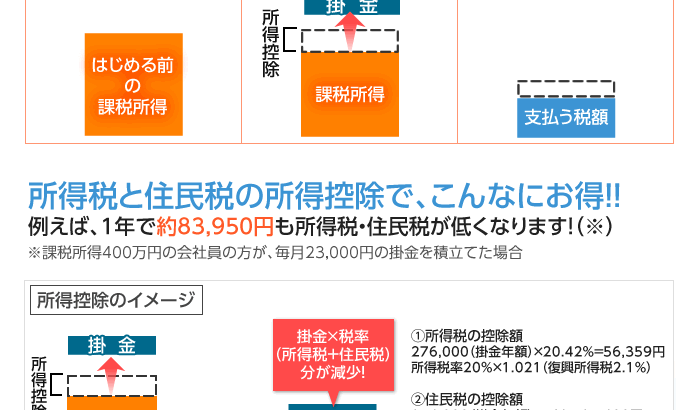
iDeCoが始まりました
ここ数ヶ月、盛んに経済誌やマネー系の媒体で取り上げられているのでご存知の方も多いかと思われます。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金の愛称です。キャッチコピーは…
「老後のために、いま、できる、こと。イデコ」
今年の1月から基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになったため、官民一体となってアピールされています(個人型確定拠出年金についてはこちら)。
このiDeCoを簡単に説明すると個人の節税商品です。支払ったときと受け取ったときに税制メリットがあります。
運用による投資商品としての側面もアピールされていますが、掛金自体が少なく、ほとんどの方がリスク商品を選択しないため、節税商品として認識していただく方が間違いありません。
では、どの程度の節税になるかというと、下記をご確認ください。

(SBI証券 WEBサイトから引用)
上記の図では、課税所得400万円の方が毎月23,000円の掛金を積立てた場合の節税額が年間84,000円程度となっています。
課税所得400万円とは、給与収入のみの方は年収600万円程度とお考えください(住宅ローン控除を受けている場合等は納税額が少なくなるため、別途試算が必要です)。
個人で積立てられる掛金の毎月の限度額は勤務先の状況によって異なりますが、中小企業に勤務されているほとんどの方の限度額は月額23,000円となるはずです。
このケースの場合、年間276,000円をiDeCoで貯金すると毎年84,000円の節税になるのです。利回りは30%となり、iDeCoが個人の最強の節税商品と言われる所以です。当然ですが、所得が高い方ほど利回りは高くなります。
つまり、節税メリットはとても大きく、所得が高い方が行わない手はありません。メリットに対しての主なデメリットは下記です。
・年間数千円程度の手数料が掛かる(節税額を考えれば特に問題無し)
・原則として60歳までは掛金を引き出せない(貯金と考えれば問題なし)
ということで、コツコツ貯金をされている方であれば、貯金するだけで税金が減るという優れものがiDeCoです。基本的に損はありません。ご興味がある方は是非ともご利用ください。
ただし、この程度だとご自分の節税だけですし、何か物足りないという中小企業経営者の方もいらっしゃるはず。そうであれば、企業型の確定拠出年金もあります。企業型は、役員及び従業員のための退職年金制度という位置づけです。
企業型には2016年3月末現在で548万人が加入しています(厚生労働省サイトより)。とはいえ、加入者のほとんどが大企業の社員ですので、中小企業にはあまり馴染みのない制度と言えます。
個人型に対する企業型の主なメリットについては、下記のとおりです。
・企業で一括管理を行うことができ、手数料は企業負担となる
・掛金が最大55,000円となる
・前払い退職金制度の導入ができる(退職金制度の導入を行わなくてもOK)
・社員の社会保険料負担の削減につながる場合がある
企業型は法人で確定拠出年金制度に加入することになるとはいえ、各社員が個人負担分として掛けることも可能です。つまり、個人負担と企業負担を兼ね備えることができる制度であり、法人にとっても個人にとっても節税商品となります。
当社グループも企業型に加入しておりますが、社員の約半数が個人負担も行って節税を受けております。
こういう国の制度でさえ、大企業と中小企業の社員で優遇差が出るのは癪なものです。現在では中小企業相手でも取り扱ってくれる金融機関もありますので、ご検討ください。
タワマン節税、やるなら今のうち!???
皆さまご存知「タワマン節税」。
昨年12月に公表された税制改正大綱において、この「タワマン節税」の封じ込めを意識したと考えられる居住用超高層建築物(高さが60mを超える、いわゆるタワーマンション)の固定資産税等の税額計算に関する改正が盛り込まれていました。
今回の改正はあくまでもタワーマンションの固定資産“税額”の計算方法に関するもので、固定資産税“評価額”に関するものではないため、原則として固定資産税評価額を基に計算する建物の相続税評価額が直ちに変わるわけではありません。であれば、まだしばらくはタワマン節税には何ら影響がないように思ってしまうのが普通でしょう。
しかし、相続税の計算に必要な「財産評価」について「そもそも」を考えると、今後一気にタワマン節税の封じ込めが行われる可能性が垣間見えてきます。
それではまず、タワマン節税について簡単におさらいしておきましょう。
「タワーマンション節税」とは相続税における財産評価方法を利用した節税手法です。
相続税では原則「財産評価基本通達」に従って、建物は固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は時価の70%程度になりますので、現預金と比べると財産の評価額が低くなります。評価額が低くなれば当然、税金も安くなるというわけです。
マンションは一軒家よりも建物の割合が大きいので、時価の70%程度である固定資産税評価額での評価割合が高くなり、土地付き一戸建てよりも評価額が下がりやすいのです。
しかもタワーマンションであれば1戸当たりの土地の持分が普通のマンションよりも小さいので、さらに評価額が低くなる傾向があります。しかも評価額は専有面積に応じて計算するため、所有する物件が眺望のよい高層階であっても1階であっても専有面積が同じであれば変わらないため、値崩れしにくい高層階を所有することで、財産価値を保ちつつ、財産評価額を下げられるという効果が得られるのです。
今回の改正では居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税等の計算について、各区分所有者の専有部分の床面積を、階層別専有床面積補正率により補正することで、財産価値の高い高層階は増税される一方で低階層は減税となります。
繰り返しになりますが、この改正はあくまでもタワーマンションの固定資産“税額”の計算方法に関するもので、固定資産税評価額は変わりませんので相続税評価額がただちに変わることはありません。
しかし、だからと言って「タワマン節税はまだまだいける!」とは言えない理由が実はあるのです。
まず、地方税(固定資産税は地方税です)の改正については、通常、総務省から改正要望があがりますが、総務省の税制改正要望にはこの改正は記載されていませんでした。つまり、相続税評価の改正が本当の目的であることは、まず間違いないのではないかと考えられます。
加えて、相続税では原則「財産評価基本通達」に従って、相続財産を評価しますが、そもそもこの「財産評価基本通達」、限りなく法律に近い拘束力を持ってしまっていることも事実ですが、その名の通りあくまでも「通達」であり「法律」ではありません。
財産評価基本通達が通達であり法律でない以上、税制改正大綱に載せる義務はありません。義務はないどころか、そもそも法律でないのですから、通達の改正を税制改正大綱に載せること自体がおかしいとも言えるのです。
つまり、総務省からの要望がなかったことを踏まえても、今回のタワーマンションの固定資産税の計算方法の改正はあくまでも相続税評価改正の伏線で、この後年内にも、いきなり税制改正大綱に記載されていない財産評価基本通達の改正に踏み込んできても何ら不思議ではないのです。
私自身は、節税だけを目的としたタワ-マンション購入を勧めることはありませんが、上手くいけばかなりの節税が可能となることも事実です。
もし、現時点でタワーマンションを利用しての節税をお考えの方は、財産評価基本通達の改正など国税の動きに注目しつつ動いていく必要があるでしょう。また、相続開始直前に購入し、相続開始直後に売却するなど租税回避の色が強い極端な事例においては否認されかねないリスクがある手法だということを十分に理解し、検討にあたっては必ず相続税に詳しい専門家にご相談なさることをお勧めします。
タワーマンション節税が本格的に封じ込められるその時は、もう間近・・・かもしれません。
年の初めに貸借対照表を眺める
貸借対照表よりも、損益計算書をよく見る。
貸借対照表の中では、現預金のみを見る。
売上高や利益が気になるのですから、当然と言えば当然です。
そして、手持ち資金が重要な訳ですから、これも当然です。
極端なことを言えば、これだけ見ていれば何となく会社の状態が分かるのだと思います。これは皆さまが数字以外の事も含めて、自社の全てを把握しているからこそ問題がない訳です。
しかし、これらを外部の人間が見るとしたらどうでしょう?
貸借対照表と損益計算書のどちらを見たいかと言われたら、もちろん貸借対照表です。
現預金は当然としても、それ以外の構成がとても気になります。他に知りたい情報があればWEBサイトを確認します。
貸借対照表を見れば、その会社と経営者の基本的な性格が分かります。
WEBサイトにはそれを補足するような情報が記載されています。
私どもはセカンドオピニオンとしてのご相談を多く受けているため、顧問契約を結んでいるお客様以外の決算書を拝見する機会が多いのですが、特に気になるのが貸借対照表です。
第三者目線からすると、歪んでいる貸借対照表が非常に多いのです。思わず「この先どうされるおつもりですか?」と質問したくなる場合があります。
「将来的には会社を売却することも考えている」と回答されたら、まず貸借対照表の歪みを正していくことをお伝えします。
例えば、ご自宅を売却する際に、荒れ放題の状態で内見してもらうのと、ちょっとした手直しやハウスクリーニングを行った状態で内見してもらうのでは、売却額に影響するはずです。これは会社でも同じことです。
そして、同じ目線で金融機関も税務署も見ています。帝国データバンクや東京商工リサーチ等の信用調査会社も見ています。
貸借対照表の歪みを探し、皆さまの会社の不利となるような点を突いてきます。
このような歪みも金融機関等は継続的な取引の中で説明が可能な場合もありますが、会社を売却するとなれば話は別です。単なる言い訳になってしまい、売却額に影響が出てしまいます。
会社売却時での例は極端とも言えますが、いつ何が起こっても外部の人間に貸借対照表の歪みを突かれないような状態にしておくことはとても大切です。
貸借対照表は皆さまの会社のこれまでの地層のようなものですが、将来に向かっての準備を表すものでもあります。損益計算書ではその準備は分かりません。
貸借対照表の構造はそれぞれなので具体的にはお伝えできませんが、将来に向かっての準備が出来ているか、年の初めに貸借対照表を改めて眺めていただくことをお勧めします。
財務省のホントの狙いとは
昨年公表された「平成29年度税制改正大綱」。一般的には配偶者控除の見直しなどが注目を集めたようですが、中小企業経営者としては最も気になる改正の1つとして「取引相場のない株式の評価の見直し」(いわゆる自社株評価の見直し)があるのではないでしょうか。
この改正、一見すると中小企業等にとっては朗報に見えます。
しかし、さすが財務省(皮肉です)。中小企業等に有利な改正と見せかけて、実は増税要素も多分に含んだ改正内容となっているのです。
皆さんご存知のように自社株評価の大きな問題点として、上場企業と違い基本的に市場流通性がないにも関わらず、実力以上に想定外に株価が高く評価されることが多々あり、事業承継を円滑に進めることが困難になるということがあります。
税理士に勧められて自社株評価をしたところ、その評価額のあまりの高さに驚き、戸惑い、その扱いに困っている経営者は少なくありません。
自社株の評価は、ザックリ言うと【配当】【利益】【簿価純資産】の3つの要素について、それぞれ【1:3:1】の比重によって算定する方法に拠られています。つまり【利益】の比重が3で最も高く、「儲かっている会社ほど評価が高くなりやすい」構造にあるわけです。
税制改正大綱では、この3つの要素の比重を【1:1:1】へと見直すとされています。これにより、誰もがまず真っ先に思うことは【利益】の比重が3から1へ下がることによって、「儲かっている会社の評価額が今までよりも下がりやすくなる」ということです。
財務省は胸を張って(表向き)「中小企業経営者の皆さん!事業承継が円滑に進むように自社株評価額が下がるように改正しますよ!」と言いたいのでしょう。
もちろん「儲かっている会社の評価額が今までよりも下がりやすくなる」ことは事実です。しかし、繰り返しですが、さすが財務省(もちろん皮肉です)です。
実はこの改正の計算式によると、自社株の評価額が今までよりも高くなる(下がりづらい)、ケースがあることに気が付きます。そして、財務省のホントの狙いは、むしろそこにあるのではないかということに思いが至ります。
では、どのようなケースで自社株の評価額が今までよりも高くなる(下がりづらい)恐れがあるのでしょうか。
■簿価純資産が大きい会社
利益の比重が下がるということは、これに伴って全体では【簿価純資産】の比重が上がることを意味します。つまり簿価純資産が大きい会社は株価が上昇する可能性があります。
例えば、株や土地を多く保有する会社において、株や土地の価額が上昇すれば簿価純資産が、より大きくなり、比例して株価評価も上昇する可能性が高まります。
言い方は適切でないかもしれませんが、何もしないで資産価値が上がったような会社については株価評価が高くなるようにしたいという、財務省の裏の意図が見えます。
■利益の圧縮により株価対策をしようとする会社
今までの評価方法では利益の比重が高かったため、評価を下げるには【利益】を痛めつける、つまり利益を圧縮したり損失を出すことが有効でした。退職金の計上や特別償却等によって株価評価を下げ、そのタイミングで株を移動することを税理士から提案されたことのある方は多いはずです。
しかし、改正によって利益の比重が下がることで、損失が計上されたとしても株価評価への影響が小さくなることになります。利益が出ている会社の株価評価を下がりやすくする一方で意図的に損益にインパクトを与えることでの株価評価対策を封じたい財務省の裏の意図がここでも見えます。
税制改正においては減税だけを行うということは、まずありません。減税を行えば、その税収減を補うべく、必ずどこかで増税を行います。
しかも、表向きは減税としていおいて、目立たぬように巧妙に裏側に増税を潜ませたりしてきます。そうした目で見ていくと、「裏」こそホントは「表」であることに気が付きます。ここを見逃さないことが税務戦略においては非常に重要です。
今年もまた1年が始まりました。時代の変化とともに税制も年々変化しており、より一層、経営を考えるうえで重要な要素となり、切り離せなくなってきています。
今年も中小企業経営者の皆様の一助となるべく、有用な情報の「表」も「裏」もお伝えしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
中小企業の労働生産性を上げるには
「日本の労働生産性は低い!」そう言われ続けています。
労働生産性とは効率を指します。つまり、日本の労働者は効率が悪い働き方をしているという訳です。
日本における就業者1人当たりの労働生産性は832万円、就業1時間当たりの労働生産性は4,718円。1人当たりではOECD加盟35カ国中22位、1時間当たりでは19位。主要先進7カ国では最下位ということ。
これが日本の労働生産性が低いと言われる根拠となっています(公益財団法人 日本生産性本部 『労働生産性の国際比較 2016年版』から引用。いずれも2015年、GDP基準改定後データより)。
当然、このデータだけで何が判断できるという訳ではありません。その国の産業構造にもよりますし、サービス残業など、表面的には隠されたデータもあるでしょう。
それでも考えざるを得ないのは、中小企業の労働生産性の実態です。
上記の数値はGDPを使用していますが、各企業の労働生産性は就業者1人当たりの付加価値(粗利益)とします。1時間当たりの労働生産性も同様です。
つまり、1人当たりの労働生産性は、自社の粗利益(人件費は除く)を従業員数で割れば算出できます。この指標は国の労働生産性と異なり、現実です。
業種や規模、ビジネスモデルにもよりますが、皆さまの会社の1人当たりの労働生産性が上記の832万円より低いと厳しい状況と考えます。
ちなみに、日本の1人当たりの労働生産性832万円を1時間当たりの労働生産性4,718円で割ると、用いられている労働時間は1人当たり1,763時間となります。
1日8時間労働で年間240日働いたとすると1,920時間(年間休日125日)。
正社員で年間1,920時間の労働というのは少ないと思いますので、月30時間の残業と仮定すると年間2,280時間。仮に1人当たりの付加価値832万円を基準にすると、1時間当たりの労働生産性は3,649円です。4,718円からは1,000円以上さがりました。
「だから何なのだ?」というのはその通りです。意味がありません。労働生産性など気にならなければ無視すればよいのです。
とはいえ、日本や各企業の労働生産性も、データを計測して判断していかなければ事実は分かりません。そして、ほとんどの中小企業の経営者は利益を上げ、かつ、効率も上げたいと考えているはずです。
労働生産性は効率を示すとお伝えしましたが、効率が上がって残業時間が減ったとしても、それ以上に利益が減ったら意味がありません。
単純に考えると、アウトプットである粗利益を上げるには、インプットである労働時間を増やさなければなりません。トレードオフの関係です。
しかし、いま世間で言われていることは、粗利益を上げて労働時間を減らす(あるいは増やさない)ことです。
純粋にトレードオフの関係で言えば、これは困難と言わざるを得ません。
労働時間については、厳密に業務内容を見直せば労働時間の1割以上はカットできると思われます。幻想ではなく、実際に無駄な業務を行っているからです。ほとんどの企業は労働時間削減のための業務内容の見直しを行っていません。
ただし、労働時間を1割カットしたところで、1人当たり粗利益は増加しません。1時間当たりの粗利益は増加するので、効率が良くなったという程度です。
極端に言えば、粗利益を追うのであれば労働時間は犠牲にしなければなりません。
第三の道としては、1人当たり粗利益も、1時間当たり粗利益も同時に上げるという点に尽きます。この解決策は粗利益を飛躍的に増加させるという点になりますが、その手法の一つは皆さまもよくご存じのように値上げです。
値上げを行えば(数が大幅に減少しなければという前提ですが)、他の要因は変わらずとも、労働生産性は上がります。
最近の風潮として、労働生産性を上げようとする場合には労働時間の削減が注目されます。電通事件後の各界の言動がその最たる例です。しかし、これだけを真に受けて労働時間を削減すると大変です。トレードオフの関係です。
本来あるべき労働時間の削減とは、労働時間を削減しても問題がない従業員は徹底して削減する。労働時間と粗利益に強い相関関係がある従業員については、直接業務により集中させるよう見直しを行うという点をよく理解すべきです。
粗利益と相関関係が強い労働時間に必要なのは、削減ではなく、増加です。
稼げる従業員と稼げない従業員は明確に分かれています。稼いでいる従業員の労働時間を一律に削減をしようというのは、自殺行為に等しいのではないでしょうか。唯一可能なのは、稼いでいる社員の労働時間のうち、誰でもできる業務を稼げない従業員にやってもらうことです。
労働時間の削減ばかりに注目して、利益が減少してしまえば、企業の存続自体が危うくなります。
では、労働時間を削減できない従業員についてはどうすべきかという点については難しいところです。当然ですが、それは給与で報いるなり、本人に意思確認すべきです。本人が無理といえば、相関関係が崩れてしまうため、他の選択肢を模索する他ありません。
なお、労働生産性が低い企業というのは、扱う商品の価格帯の幅が大きいように思います。
高い商品から低い商品まで売ろうとしている。そのため、数が出る低い価格帯の商品を多く扱う従業員の労働生産性が極めて低く、高い商品を多く扱う従業員の労働生産性が高いというような感じです。
このような企業の労働生産性というのは、従業員というよりも企業側の問題です。
これに対して、例えば幅の狭い価格帯の商品を売っている企業は、その従業員の成果がダイレクトに労働生産性に直結します。
また、直接業務(営業や製造)と間接業務(総務経理)の従業員の比率も大きく影響します。
労働生産性を上げるといっても、それぞれ企業の構造次第です。そして、自社の実際のデータを把握せずして、労働生産性を上げる施策を実行するなどあり得ません。繰り返しますが、自殺行為です。
逆に、データなど無くとも、値上げをすれば結果として労働生産性は上がるのです。
今後も生産性、生産性という声が様々なところから聞こえてくるかもしれませんが、下手な対応を行うと大変な目に会う可能性があるということは頭の片隅においていただければと考えます。